はじめまして。私(@hoheikun_cheme)は、大学院卒業後に化学メーカーで技術開発職として働いています。
化学メーカーに就職すると、具体的にどのような仕事に携わることになるのでしょうか? 「研究職」や「開発職」など、いくつかの職種が思い浮かぶかもしれません。
本記事では、そうした疑問に答えるべく、「研究職」「開発職」の違いをわかりやすく解説します。それぞれの役割や特徴を理解し、自分に合ったキャリアを考える参考にしてください。
 歩兵くん
歩兵くん研究職と開発職は似てるようで違いますが
どのような違いがあるのでしょうか
「研究職」とは
「開発職」とは
「研究職」と「開発職」の違いとは?
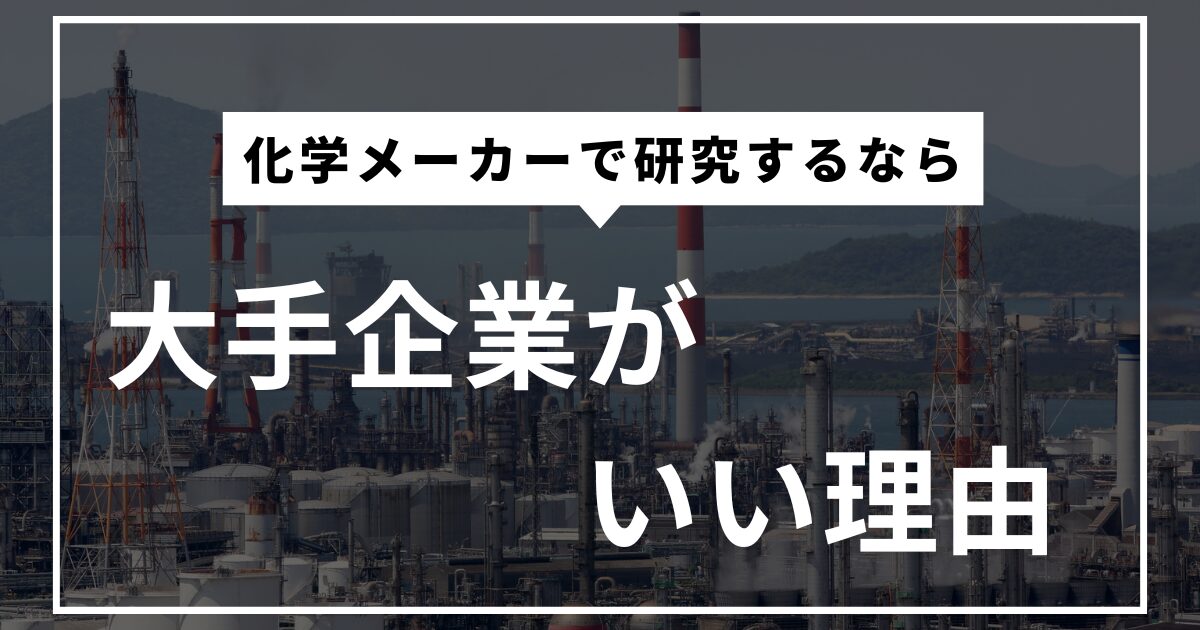
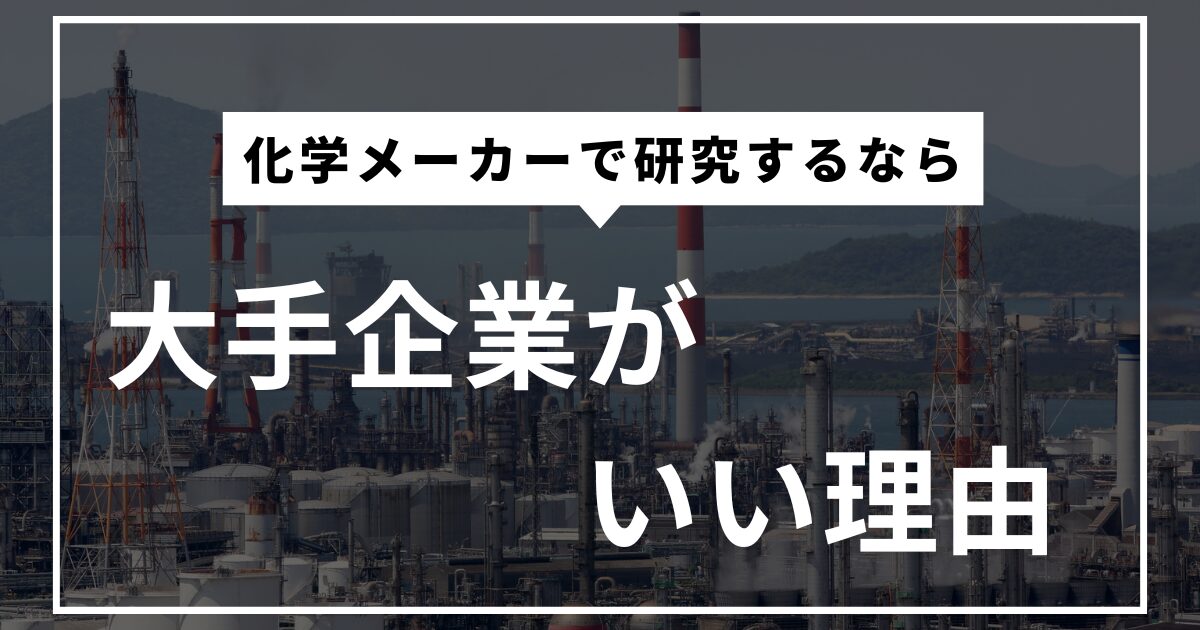
研究職とは?


研究職は、新しい知識や技術を発見することを目的に、実験や調査を行う仕事です。大学時代の研究の延長にある業務であり、未解決の問題に挑む力が求められます。
発想力は、よく氷山に例えられます。水面上に見えるひらめきの裏には、膨大な思考が隠れています。つまり、普段から考えることを楽しめる人でなければ、研究職を続けるのは難しいかもしれません。探究心が強く、好きな分野に没頭できる人は研究職に向いてます。



新しいものを生み出すための発想力が求められます
研究の内容は「基礎研究」と「応用研究」に大別されます。
基礎研究
「基礎研究」は、新しい原理・理論・素材などの発見・解明を目的とする研究です。基礎研究から実用化までの道のりは長いですが、新しい価値を生み出すために欠かせない研究といえるでしょう。



より大学の研究に近い仕事といえますね


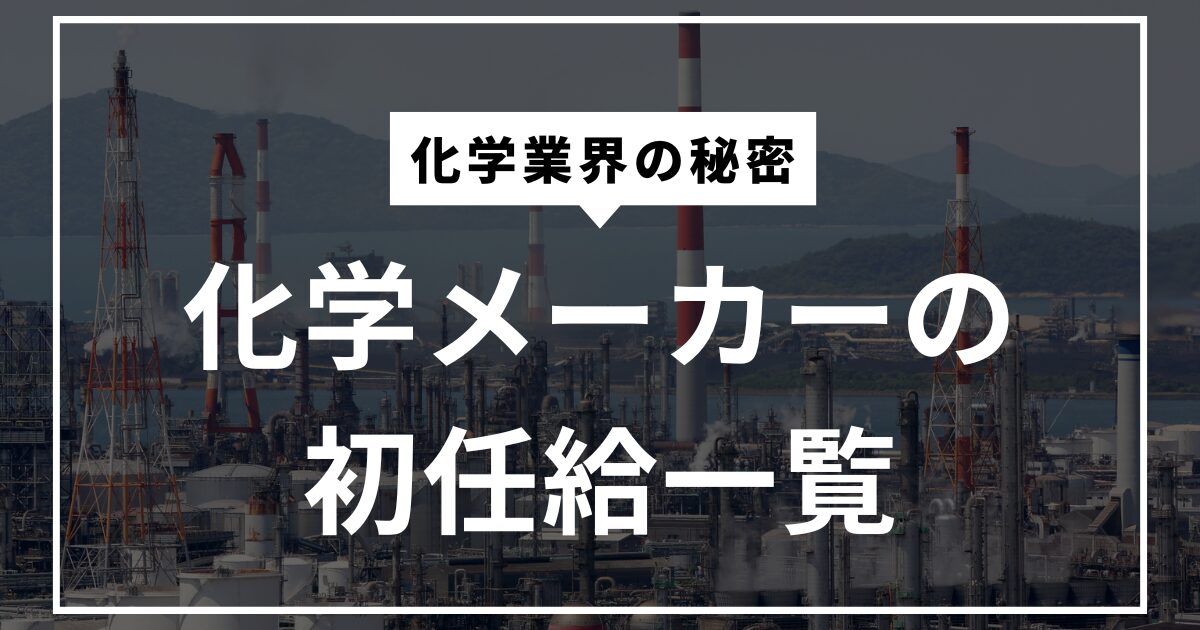
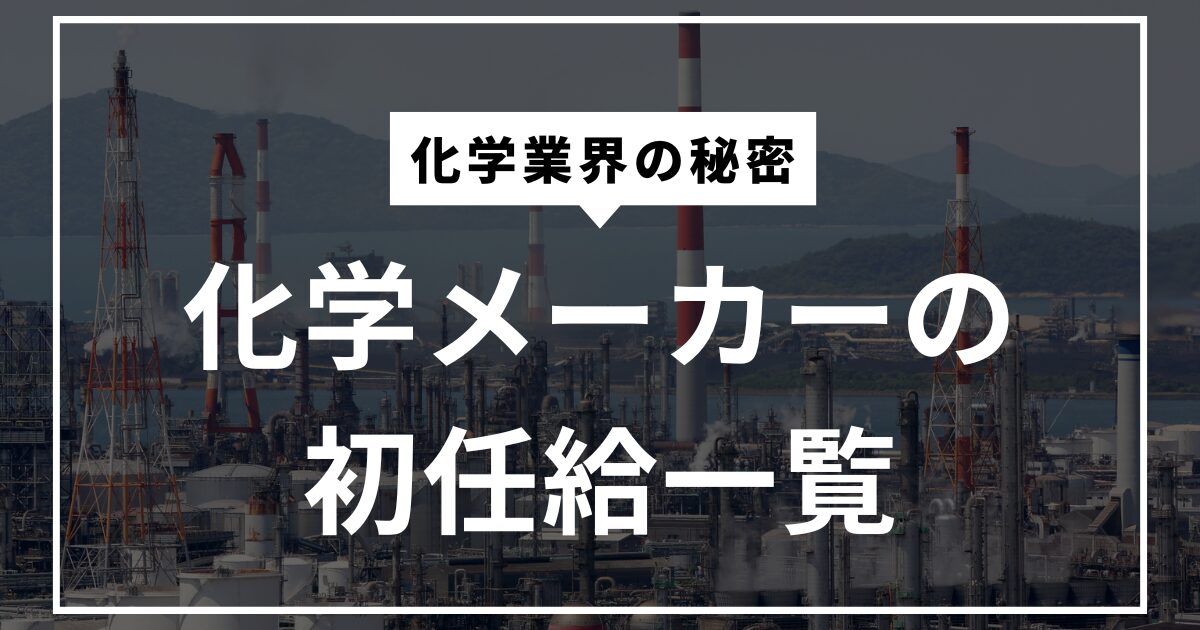
応用研究
「応用研究」は、基礎研究で発見・解明された成果の実用化を目的とする研究です。具体的には、基礎研究の成果を、目指すサービス・製品として実用化を目指します。また、すでに実用化されている方法の応用が研究されるケースもあります。 応用研究は企業で実施されることも多く、その場合は、品質向上・ 顧客満足度向上・コスト削減など、企業の利益にも配慮して研究する必要があります。



応用研究は社会のニーズに合わせた調査もします


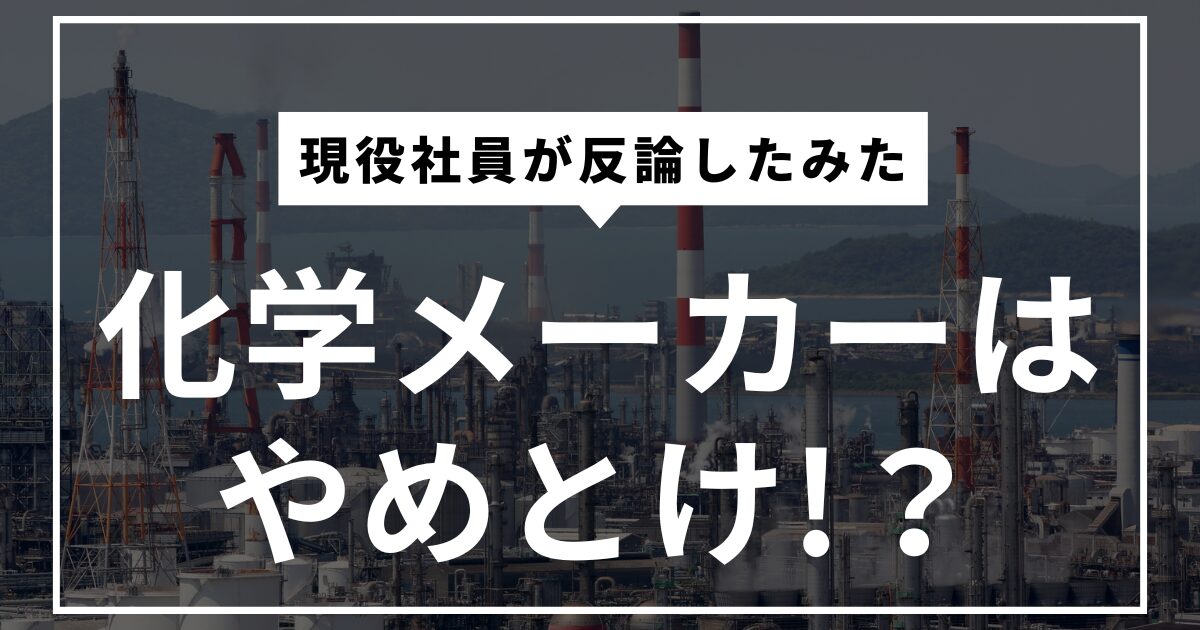
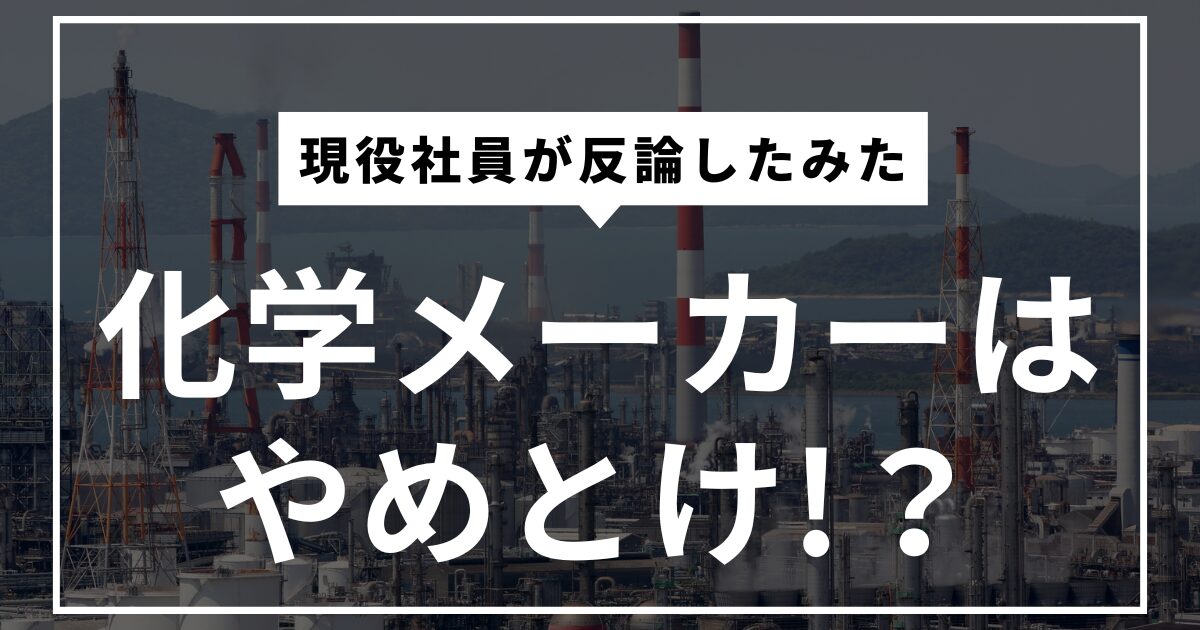
開発職とは?


開発職は、既存の技術や製品を基に、新しいものを生み出すことを目的とした仕事です。製品開発やソフトウェア開発などが含まれ、主に企業で働くことが多いです。開発職においては、製品が市場に出ることを意識しながら、顧客のニーズに応じた改善・改良を行っていきます。そのため、常に社会の動向を敏感に感じとり、社会のために何を生み出せばよいのか考えられる人が向いています。



研究職より社会のニーズに合わせた探求を行う仕事ですね
技術開発職
「技術開発職」は、既存の技術や製品を基に、新しい価値を生み出すことを目的とした仕事です。製品開発やソフトウェア開発などが含まれ、主に企業で活躍します。技術開発職では、市場への展開を意識しながら、顧客のニーズに応じて、研究職が生み出した知識や技術を応用・改良し、実用化を進めていきます。
また、技術開発職には高度な専門知識が求められるため、専攻分野を活かして働きたい理系学部出身の就活生に人気の職種の一つです。



私も技術開発職なので
気になることがあれば質問してください
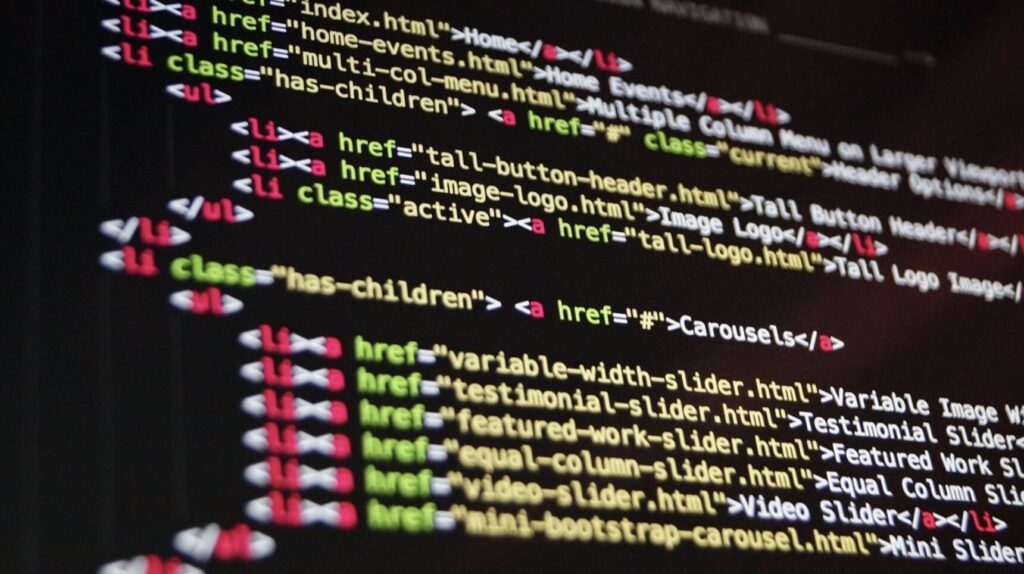
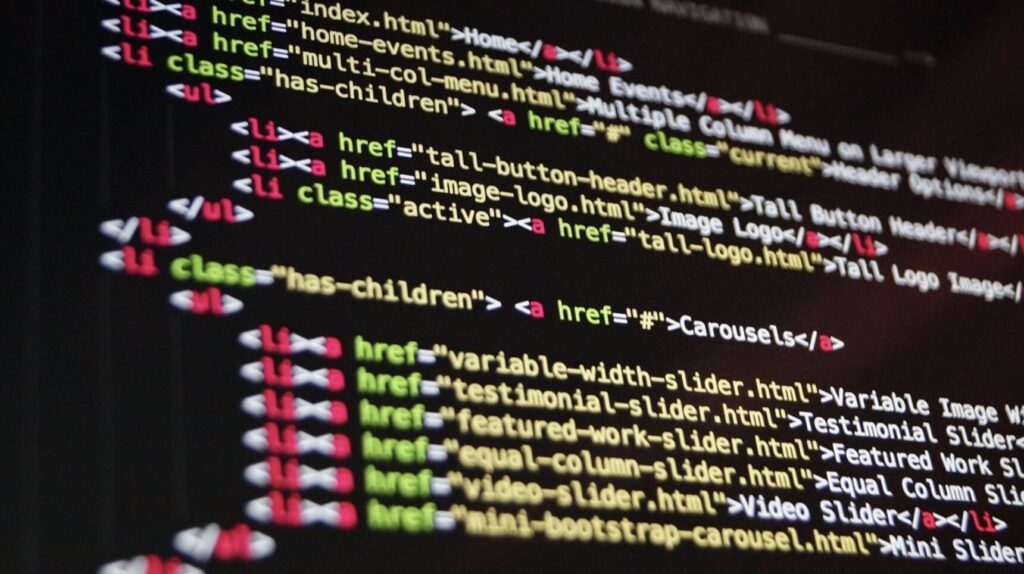
商品開発職
「商品開発職」の仕事は、ひとことで言えば新しい製品を生み出す仕事です。既存製品を応用して新たな製品を開発する場合と、ゼロからまったく新しい製品を開発する場合があります。
商品開発職は、研究職から成果を引き継ぎ、それを実際の製品として形にする役割を担います。市場のニーズを分析し、マーケティング戦略を立案するほか、生産コストの試算も重要な業務です。
研究開発職や生産部門、また営業部門など、あらゆる関係部門と調整をとりながら売れる製品を開発することが求められます。また、商品開発職は新製品を生み出していくため、モノづくりのど真ん中の仕事をすることができます。



商品開発職は新製品を世の中に出すというやりがいのある職種ですね
研究職と開発職の違いを比較





研究職と開発職の違いを表で一覧にしてみました!
| 項目 | 研究職 | 開発職 |
|---|---|---|
| 自由度 | ○ 会社の方針の中で研究したいことをする | ✕ 製品化するものに合わせて開発を行う |
| 忙しさ | △ 学会、研究発表前は資料作成あり | ○ 開発の納期があり忙しい |
| 実用度 | ✕ 基礎研究は実用性が想像しづらい | ○ 自分で開発したものが製品になる |
| 規模 | ✕ 基本ラボサイズ | ○ 工場での試験もあり、大きなお金が動く |
| 業務内容 | 0→1を作る | 1→10を作る |
Q. どっちの方がやりがいある?
A. 人によります。
テーマの自由さについては間違いなく研究です。基本開発は開発するものが決まっているのに対し、研究側は何をやっるかをある程度自由に決めることができます。自分でテーマを立案し、スケジュールを立て、試験をし、結果を出すのが好きな人は研究職が向いています。
モノづくりのど真ん中で製品開発をしたいなら開発です。研究から移管された知識・技術をもとにして新製品の開発につなげます。自分が考えたものが形になり、世の中に出ていくところをみるのが好きな人には、開発が向いていると思います。
Q.どっちの方が忙しい?
A. 開発職です。
新製品を出す時期は決まっており、私の会社では半年に1回程度、新製品を出しています。納期が決まっているため、それに向けて計画を立てて、実験→試作→分析・評価のスケジュールを立てて、開発していくことになります。
一方、研究はあまりにきつい締め切りはないと思います。外部との共同研究や、国家プロジェクトであれば、期限付きのものもありますが、基本は会社内での締め切りであり、それほどプレッシャーは大きいものではありません。



私も技術開発職にいますが
締め切りが厳しいときが多いですね、、、
Q.どっちの方が出世しやすい?
A.人にもよりますが、開発職の方が出世しやすいです。
私の会社では、開発職の方が出世しやすい傾向にあります。その理由の一つは、担当するテーマの期間の違いです。先述の通り、研究職よりも開発職の方がプロジェクトのスパンが短く、成果を出しやすい傾向にあります。仕事は成果によって評価されるため、結果を出しやすい開発職の方が昇進の機会を得やすいのです。
また、開発職は異動の選択肢が広く、研究職に加えて、生産部門や技術営業など、さまざまな部署への異動の可能性があります。これにより、多様な経験を積み、管理職としての適性を高める機会が増えるため、出世しやすくなります。一方、研究職の異動先は開発職など限られた範囲にとどまり、異動の機会が少ない人も多いです。その結果、開発職の方が研究職よりも昇進しやすい傾向にあると考えられます。



開発職の方が利益を出していることが多く
研究は時間がかかるため、「金食い虫」と考えられがちです。。。
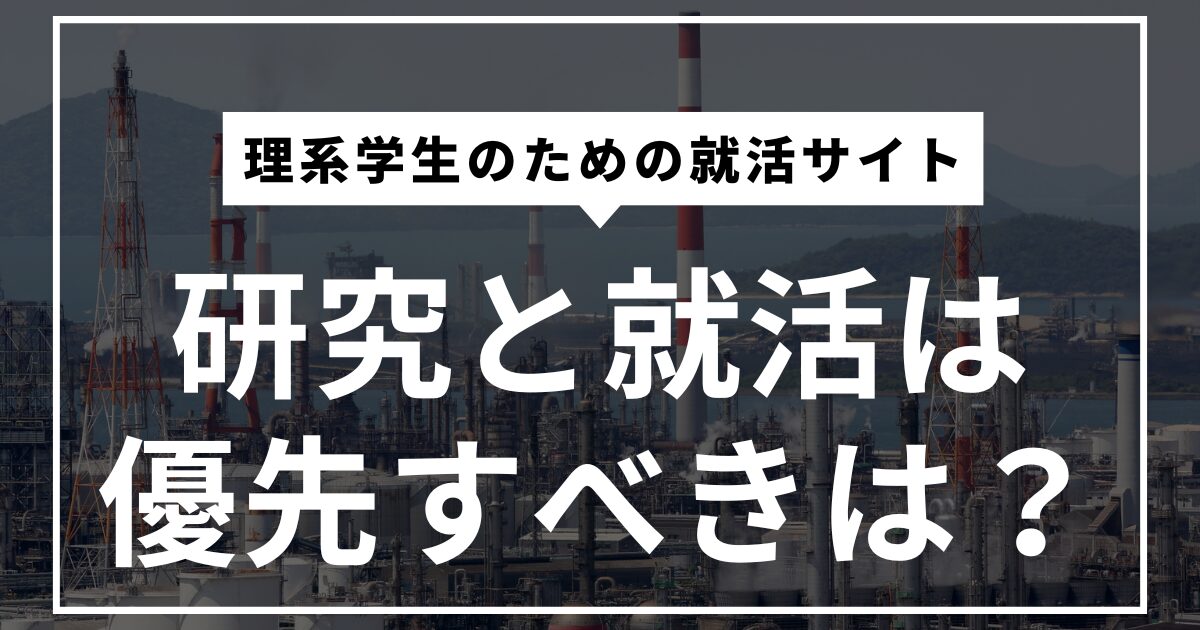
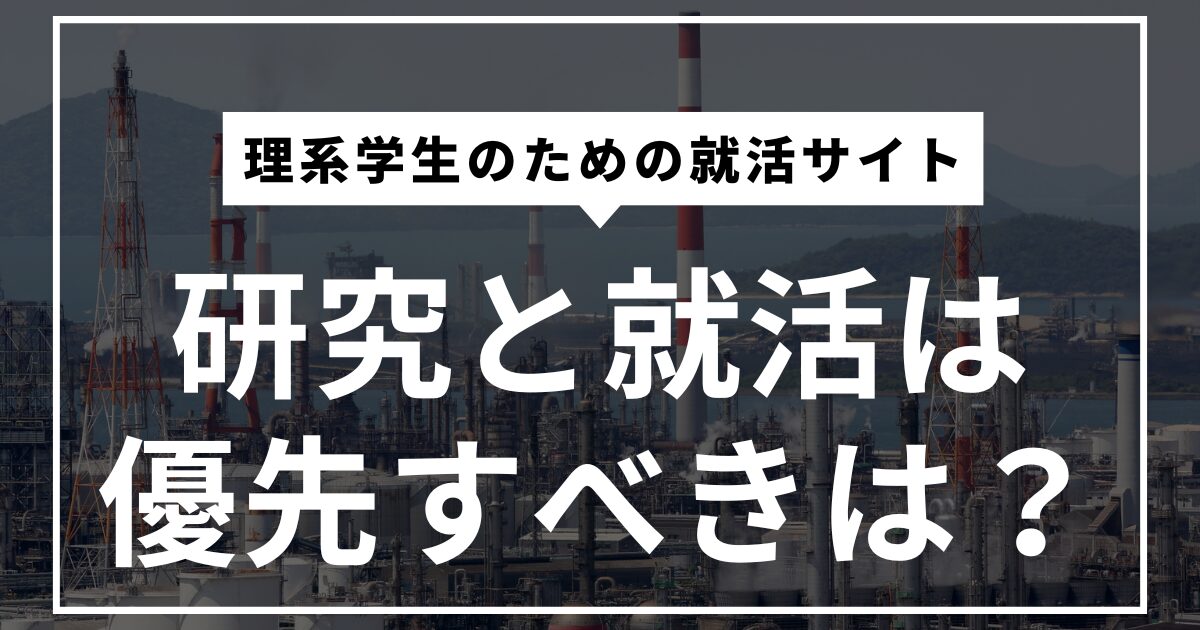
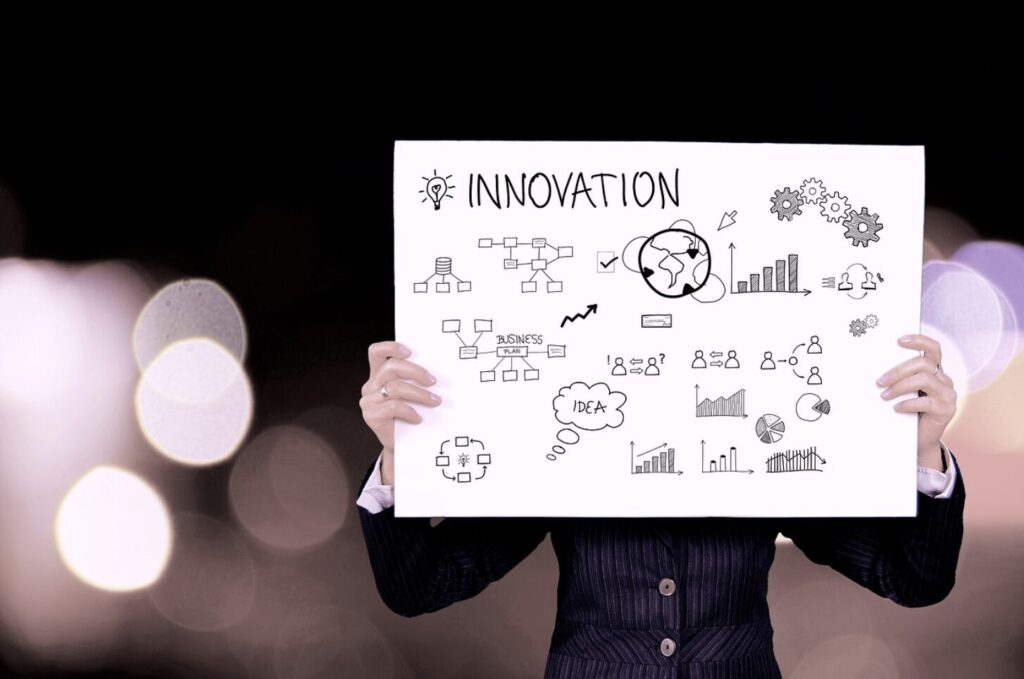
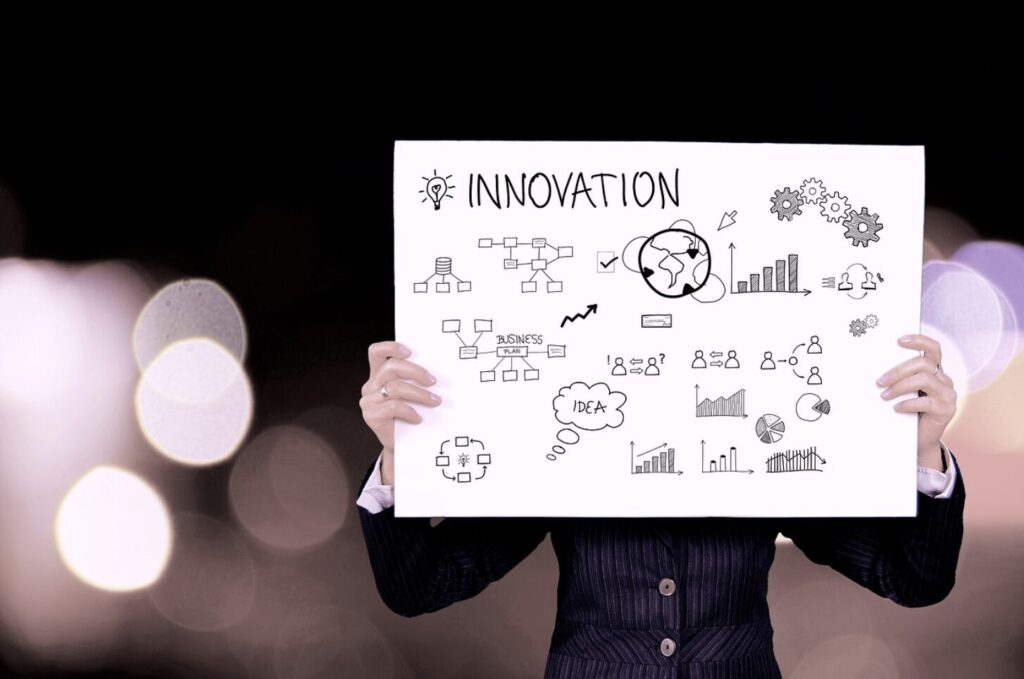
まとめ
「研究職」と「開発職」の違いについて説明しました。研究職は基礎研究を通して、新たな知識や技術を生み出すことを目的とし、開発職はモノづくりのど真ん中で新製品開発に携わる役割を担います。研究職と開発職は共通点も多く、どちらに進むべきか悩む方も多いでしょう。本記事がそのような方の参考になれば幸いです。



ここまで読んでいただきありがとうございます
よかったら他の記事もご覧ください
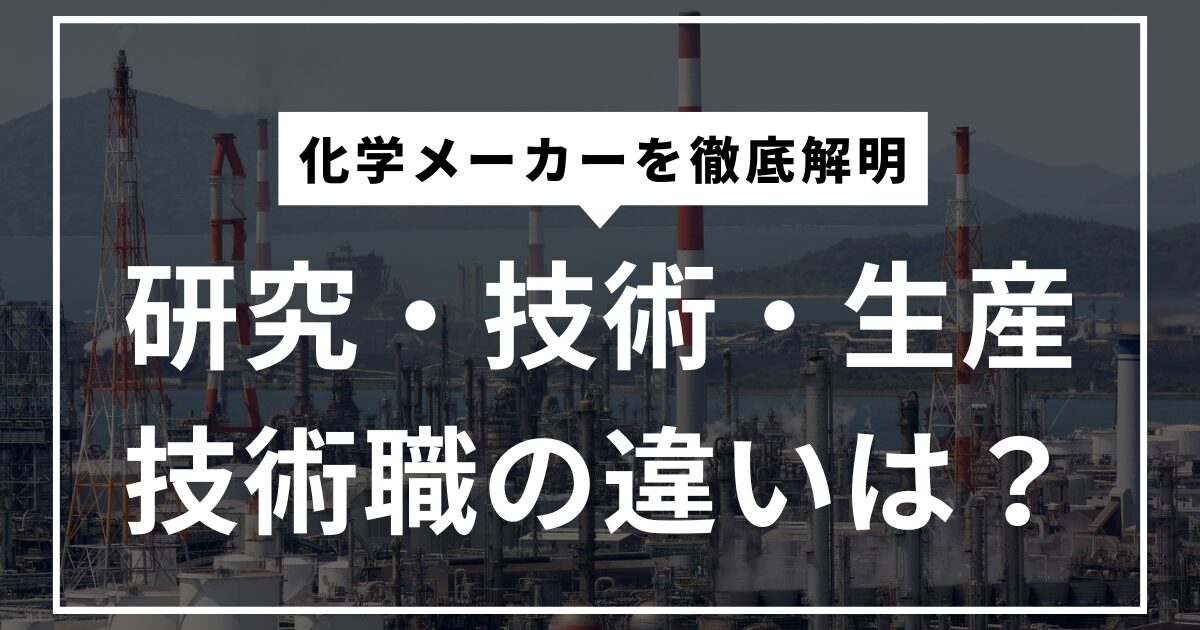
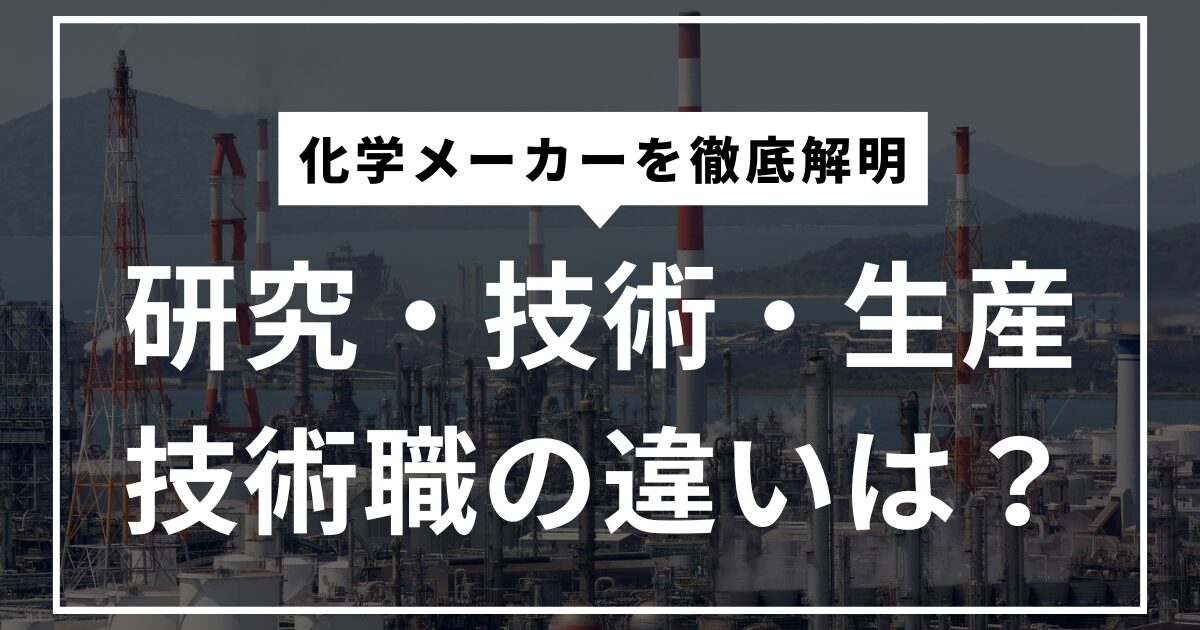
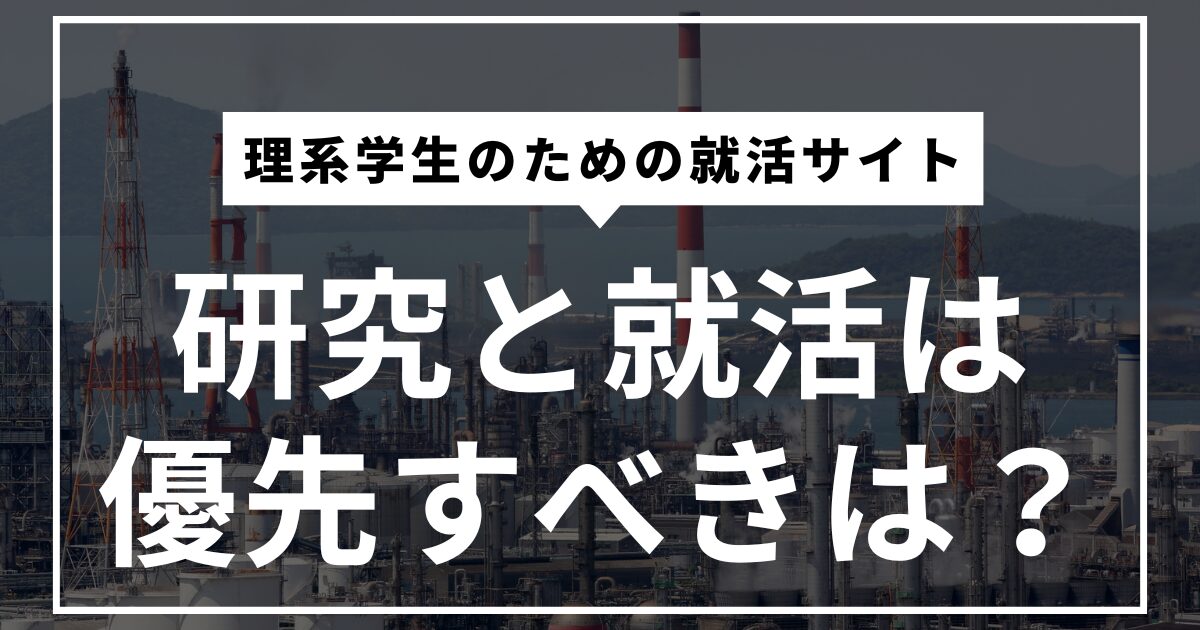
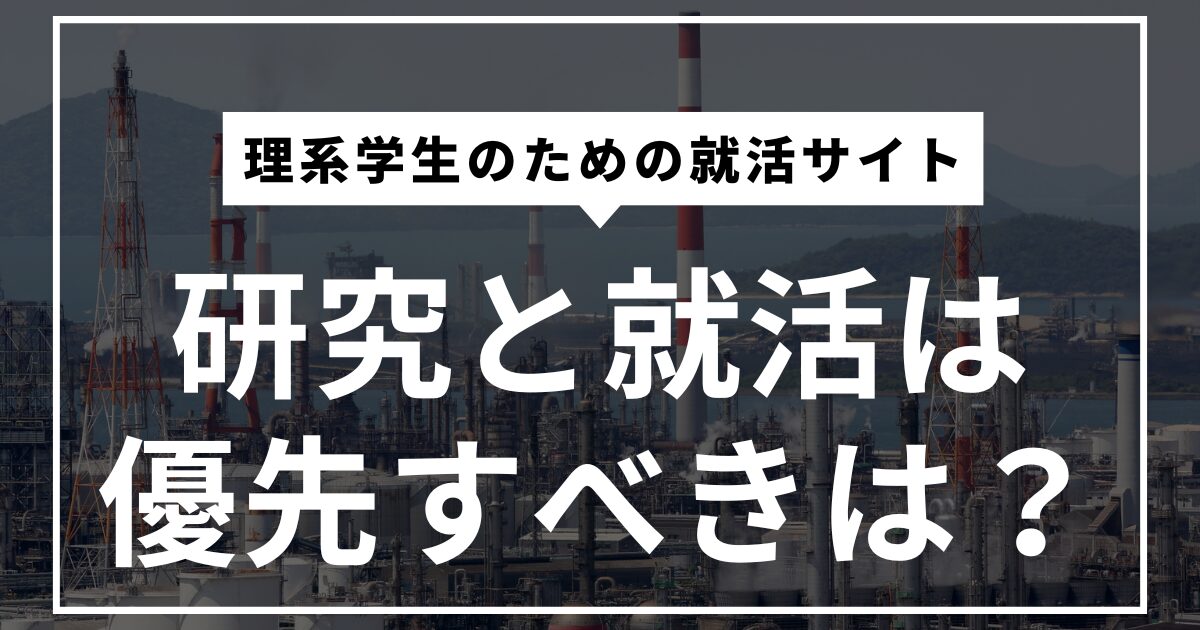
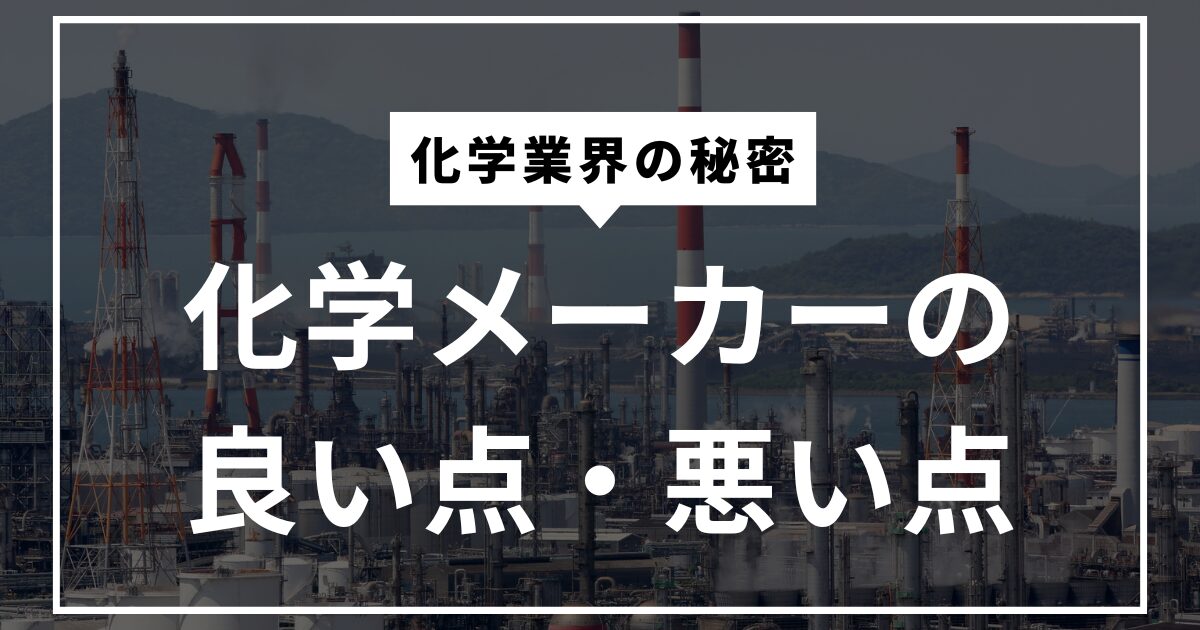
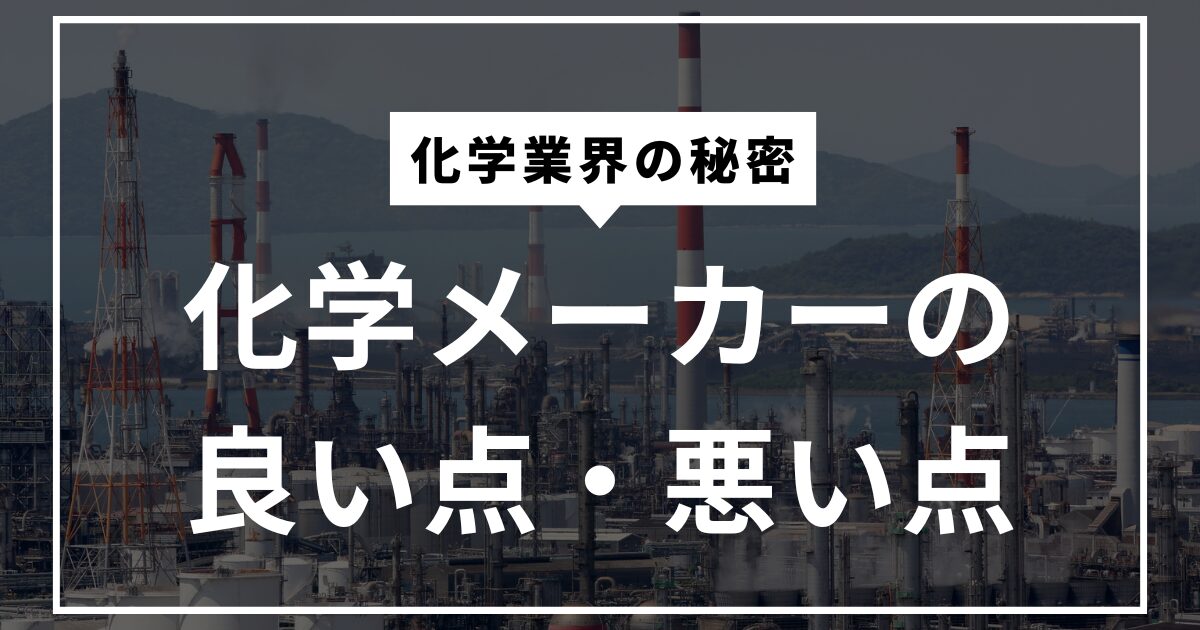

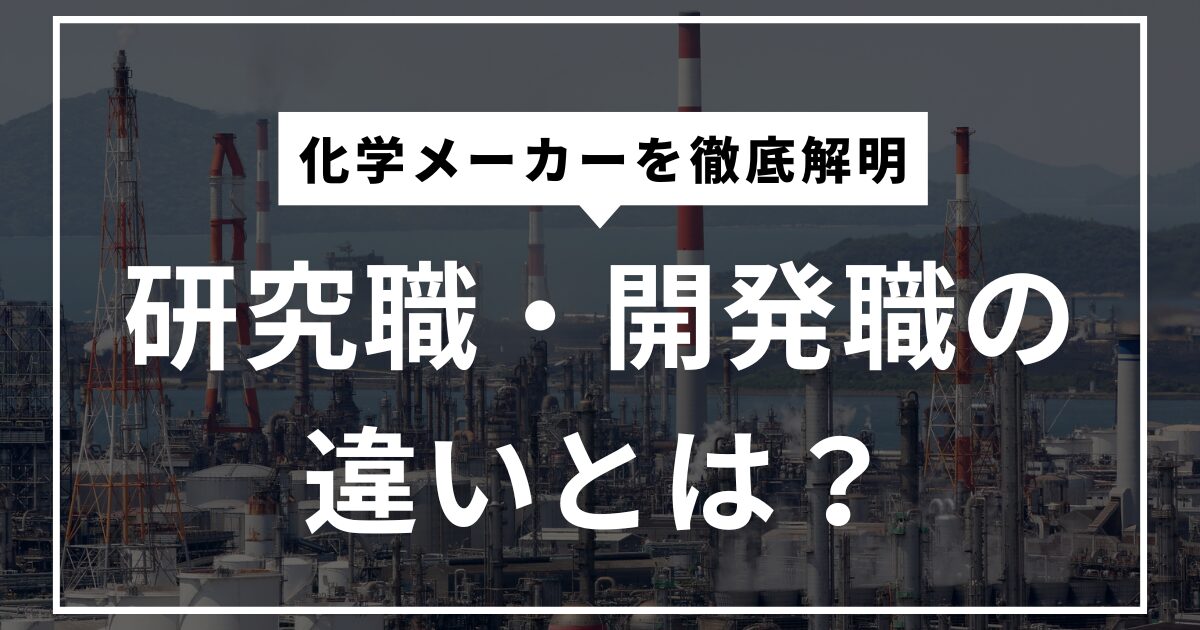
コメント